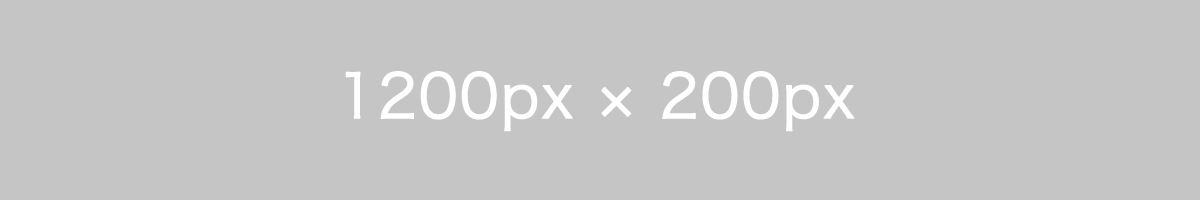相談支援員が障害者グループホームで重要!書類を作成してもらう
障害者グループホーム(共同生活援助)への入居を考えるとき、相談支援員(相談員)を付けるのが一般的です。相談員が書類作成したり、調整をしたりすることでようやく障害者グループホームに入るための準備が整います。 ただ場合によっては、相談員を見つけるのが困難なケースがあります。そのため、「相談支援員がいない場合であっても障害者グループホームへ入居する方法」を知っておく必要があります。相談員がいない場合、自分で入居先を見つける必要があるものの、施設の協力によって入居可能になるケースがあります。 それでは、障害者グループホームの利用でどのように相談支援員を活用すればいいのでしょうか。グループホームで重要な…

相談支援員を変えたい!合わない・役に立たない相談員の変更方法
障害者向けのサービスを利用するとき、ほとんどの人で相談支援員(相談員)を付けることになります。相談支援事業所に依頼し、相談員がさまざまな手続きをすることによって障害福祉サービスを受けられるようになります。 ただ場合によっては、いまの相談員と合わないため、相談員を変えたいと考える場合があります。相談支援員を変えることについて、理論的には可能です。ただ、役に立たない相談員を変えるとはいってもルールがあり、特定のタイミングでなければ変更できません。 それでは、最悪な相談支援員を変更するにはどうすればいいのでしょうか。障害福祉サービスを利用している人について、相談員の変え方を解説していきます。 相談員…

就労継続支援A型の給料・年収・手取り:社会保険は加入できる?
障害の程度が軽度であるものの、一般就労が難しい場合、就労継続支援A型(就労A)を利用することで給料を得ることができます。就労Bの工賃とは異なり、最低賃金が守られて時給が計算されるため、それなりの賃金になります。 ただ短時間労働になるため、就労継続支援A型を利用するにしても一般就労に比べると給料・年収は少ないです。そうしたとき、平均月収はどれくらいになるのでしょうか。また実際の手取りや社会保険への加入はどのようになるのでしょうか。 就労Aを利用するとき、これらお金のことを事前に理解しなければいけません。そこで、就労継続支援A型での平均賃金や手取りについて解説していきます。 賃金はどこから?生産活…

就労継続支援A型は何歳まで利用できる?年齢制限と65歳以上の利用
障害者であれば、一般就労が難しくなります。そうしたとき、軽度の障害者であれば就労継続支援A型(就労A)を利用して働き、最低賃金が守られるようにお金を得るのが一般的です。 ただ通常、障害福祉サービスには年齢制限があります。これは就労継続支援A型も同様であり、65歳など特定の年齢が基準になっています。ただ就労継続支援A型の場合、条件を満たせば70歳など、65歳以上であっても継続して利用できるようになっています。 それでは、就労継続支援A型の年齢制限や高齢での利用条件はどのようになっているのでしょうか。何歳から何歳まで就労Aを活用できるのかについて解説していきます。 原則の利用は18歳から65歳まで…

就労継続支援A型・B型で完全在宅勤務は可能?在宅ワークの作業所内容
障害者であれば、外に出るのが困難なケースがよくあります。そうしたとき、就労継続支援A型(就労A)や就労継続支援B型(就労B)などの作業所で働くにしても、在宅ワークにて可能かどうか考える人がいます。特に精神障害者の場合、完全在宅勤務のほうが適切なケースは多いです。 これについて、少ないながらも在宅ワークにて仕事を行える就労A・就労Bは存在します。そうした作業所を利用すれば、外出しなくても仕事を行えます。ただ、事業所へまったく出向かずに利用するのは不可能です。そのため、住んでいる近くに在宅ワーク可能な作業所がなければいけません。 それでは、就労継続支援A型・B型で在宅ワークを行う作業所の特徴は何が…

就労継続支援A型の仕事内容や選び方!1日の流れはどうなる?
障害の程度が軽度なのであれば、就労継続支援A型(就労A)によって仕事が可能です。障害特性を理解した作業所で働くことになるため、一般就労できる状態ではなくても問題なく仕事が可能です。 このとき、作業所によって業務内容は大きく異なります。そのため就労Aを選ぶとき、まずは仕事内容を確認しなければいけません。また、仕事時間も就労継続支援A型によって違うため、事前に見学・体験利用することで1日の流れを把握するのは重要です。 それでは、就労継続支援A型の仕事内容や選び方としては何があるのでしょうか。就労Aの業務内容や優れた事業所の選択法を解説していきます。 どんな仕事?就労Aの業務内容は多岐にわたる それ…

就労継続支援A型で非雇用型(雇用契約を結ばない)で働くには?
就労継続支援A型(就労A)を利用するとき、雇用契約を結んで働くことになります。これにより、最低賃金が守られた状態にて作業所で仕事をします。 ただ就労継続支援A型で仕事をするとき、事業所によっては雇用契約を結ばない形式にて働ける場合があります。非雇用型での仕事になりますが、この場合は体調などに不安がある場合であっても、就労継続支援A型での仕事を経験できます。 それでは、就労Aの作業所で雇用契約なしで働くときは何を考えればいいのでしょうか。就労継続支援A型での非雇用型について解説していきます。 通常、就労Aは雇用契約が必要 障害者が就労継続支援A型を利用するとき、通常は雇用契約を結ぶことになります…

就労継続支援A型でクビに?利用者解雇が存在する
就労継続支援A型(就労A)を利用する場合、雇用契約を結ぶことになります。そうしたとき、場合によっては就労Aを解雇されることがあります。 障害福祉サービスとして作業所で働くため、通常は急な解雇はありません。ただ雇用契約の内容を守れなかったり、事業所側の都合であったりしてクビになるケースがあるのです。 それでは、就労Aの利用者で作業所をクビになるパターンとしては何があるのでしょうか。就労継続支援A型で利用者が解雇されるケースを解説していきます。 就労継続支援A型で解雇は存在する すべての障害福祉サービスについて、利用停止を食らう場合があります。最もわかりやすいのは暴言・暴力がある障害者です。この場…

生活保護は就労継続支援A型を利用可能?働き損になるのか?
就労継続支援A型を利用する人の中には、生活保護受給者がいます。障害者で生活保護を受けている人は非常に多いため、これについては特に不思議ではありません。 そうしたとき、最低賃金を下回るのであれば就労継続支援A型を利用しても生活保護の打ち切りになることはありません。一方でそれなりに多く稼げば生活保護の対象外になりますが、住民税の非課税世帯であるため、引き続き多くの特典を利用できます。さらに、働き損もありません。 それでは、生活保護の受給者が就労継続支援A型を利用するときに何を考えればいいのでしょうか。生活保護受給者が就労Aを利用するときのポイントを解説していきます。 生活保護で就労Aを利用するのは…

就労継続支援A型の面接内容や履歴書の書き方:服装や聞かれることは?
これから就労継続支援A型(就労A)にて働きたいと考えている障害者について、通常はすべてのケースで事業所を見学・体験することになります。このとき、同時に面接を受けます。場合によっては、履歴書の提出を求められることもあります。 そうしたとき、面接では何を聞かれるのでしょうか。服装はどうすればいいのでしょうか。履歴書の書き方は何があるのでしょうか。 就労Aの作業所で働くとはいっても、場合によっては落ちることがあります。そこで、就労継続支援A型での面接をどのように乗り切ればいいのか解説していきます。 就労Aの面接は一般的に簡単 障害者でも健常者でも、一般企業の正社員で働くとなると難易度が高いです。それ…