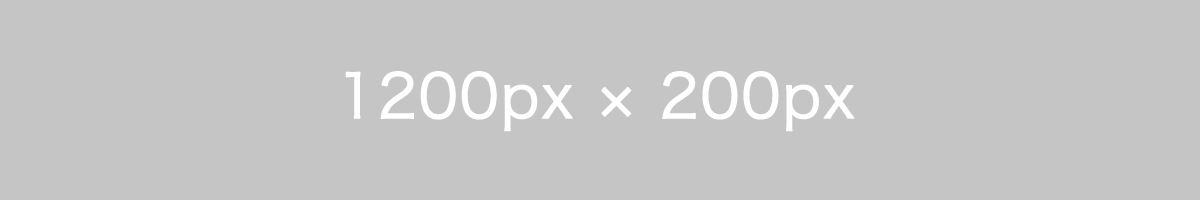就労移行支援の年齢制限:18歳未満や65歳以上の利用は可能?
企業就職で重要な障害福祉サービスに就労移行支援があります。就労移行支援には年齢制限があり、一般的には18~64歳で利用可能です。 ただ例外があり、場合によっては18歳未満でも利用できます。一方、高齢者の利用者はほぼいないため、就労移行支援の活用を考える必要はほぼありません。 それでは就労移行支援を実際に利用するとき、どのように年齢制限を考えればいいのでしょうか。就労移行支援の利用年齢について解説していきます。 18~64歳の利用となる就労移行支援 すべての障害福祉サービスに年齢制限があります。これは、障害福祉サービスは若い人向けのサービスだからです。就労移行支援については、以下の人が利用対象に…

知的障害者が就労移行支援で一般就労し、働くときの考え方
知的障害者であっても一般就労を目指すのは普通であり、会社で働くことで活躍している人はたくさんいます。そうしたとき、就労移行支援を利用することで企業就職を目指します。 身体障害者や精神障害者とは異なり、知的障害者で正社員の割合は少ないです。また行える仕事内容も限られやすいです。ただ、そうした中でも一般企業で働くことで仕事を行うのです。このとき、社会マナーや就労後のサポートを含めて就労移行支援が担います。 それでは知的障害者が一般就労を行うとき、何を考えればいいのでしょうか。知的障害者が就労移行支援を利用するときの考え方を解説していきます。 軽度の知的障害者が一般就労を目指す 知的障害者とはいって…

就労移行支援で子供を保育園に入れるのは可能!注意点は何?
子育て中の人であっても、障害者で就労移行支援を利用したいと考えるのは普通です。そうしたとき、子供を保育園に入れることで就労移行支援を利用できるようになります。 配偶者(夫・妻)がいて働いていたとしても、シングルマザーであったとしても、障害者は子供を保育園へ入れやすいです。また就労移行支援を利用することで働けるようにすれば、収入を得られます。もちろん障害者であるのは変わらないので、働いても継続して保育園を利用可能です。 それでは、小さい子供がいて就労移行支援を利用したい場合、どのように考えればいいのでしょうか。就労移行支援と保育園を併用するときの考え方を解説していきます。 就労移行支援で保育園の…

就労移行支援の利用期間は2年:延長や2回目の再利用・リセットは?
障害者が一般就労を目指すときに重要な障害福祉サービスが就労移行支援です。ただ、このとき気になるのが就労移行支援の利用期間です。 一般的には、就労移行支援の利用期間は2年間までとなっています。ただ場合によっては延長が認められます。また中には再利用を考えている人がいるため、このときは2回目や3回目の利用が可能なのか気になります。なお、場合によってはリセットも可能であるため、事前に基準を理解するのは重要です。 それでは、就労移行支援の利用期間や延長、再利用、リセットはどのように考えればいいのでしょうか。ここでは就労移行支援の期間について解説していきます。 原則、就労移行支援の利用期間は2年 身体障害…

就労移行支援はトライアル雇用と併用可能!注意点は何か?
障害者が就労移行支援を利用することにより、一般就労を目指すことができます。このとき、一般就労に向けた第一歩としてトライアル雇用を利用できます。 就労移行支援の利用中にトライアル雇用の併用は可能です。トライアル雇用によって自分に合った職場かどうか確認しつつ、就労移行支援によるサポートを受けられるのです。ただ場合によっては、就労移行支援を一時的に停止した方がよいケースもあります。 それでは就労移行支援の利用中にトライアル雇用を活用する場合、何に気を付ければいいのでしょうか。就労移行支援とトライアル雇用の併用について解説していきます。 就労移行支援とトライアル雇用を併用できる 一般企業での就職を目指…

無職のニート・引きこもりで就労移行支援を利用するメリット
大人で無職のニート・引きこもりになっている人がいます。「莫大な資産が既にある」など、本人の意思によって働いていないのであれば問題ありません。ただ、低所得者にも関わらず大人のニート・引きこもりである場合は社会復帰を考えなければいけません。 こうした大人の無職では、ほとんどのケースで何かしらの精神疾患を抱えています。そうしたとき、就労移行支援を利用することで徐々に外へ出るのに慣れ、最終的に企業就職を果たすのは大きな意味があります。 それでは、大人の無職はどのように考えて就労移行支援を利用すればいいのでしょうか。利用の流れや料金、その他の注意点を含めて解説していきます。 精神障害者は就労移行支援を利…

生活保護で就労移行支援を利用できる!交通費・昼食代は自己負担
生活保護を受けている人であっても、将来は企業就職して社会復帰したいと考えるのは普通です。そうしたとき、一般就労するためのトレーニングとして就労移行支援を利用できます。 高齢者でないにも関わらず生活保護というのは、ほとんどのケースで障害者です。健常者の場合、生活保護に頼らずアルバイトでもいいので働いているのが普通だからです。そうした障害者について、就労移行支援を利用することで社会復帰できます。 それでは、生活保護で就労移行支援を利用するときは何を考えればいいのでしょうか。生活保護受給者で就労移行支援を利用するときの考え方を解説していきます。 生活保護受給者でも就労移行支援を利用可能 いま低所得者…

大学生・在学中に学校と就労移行支援を併用する流れ
大学生や短大生、専門学校生など、いま学生として在学中の人はたくさんいます。そうした学生の中には、うつ病や発達障害などの精神疾患を抱えている人がいます。身体障害者もいるかもしれません。 そうした場合、在学中であっても就労移行支援を利用することで将来の企業就職に備えることができます。障害者では健常者よりも一般就労が難しいです。また、働きはじめた後についても企業への定着が厳しいです。そこで、障害者枠の活用も検討し、就労移行支援を利用するのです。 ただ、学生が就労移行支援を利用するときの注意点がいくつか存在します。そこで、何を考えて就労移行支援を活用すればいいのか解説していきます。 卒業の年に学生は就…

就労移行支援の工賃問題:賃金・収入なしで生活費はどうする?
一般就労を目指す障害者の多くが利用する障害福祉サービスに就労移行支援があります。ただ就労移行支援を利用するとき、一つの問題点として「工賃を得られない」ことがあります。工賃ありで働くのは基本的に無理であり、収入を得られる場所ではありません。 そのため生活費を何とかしたい場合、給付金を得たり、その他の障害福祉サービスを利用したりしなければいけません。つまり、他の方法によって生活費を確保する必要があります。 それでは就労移行支援を利用する障害者について、収入の問題をどのように解決すればいいのでしょうか。就労移行支援での収入について解説していきます。 就労移行支援で工賃・給料は存在しない 障害者が就労…

就労移行支援でクローズ就労を行うには?オープン就労と勝手が異なる
障害者が就職活動をするとき、就労移行支援を利用する人が多いです。このとき、障害者であることを開示せずに働く方法としてクローズ就労があります。 就労移行支援を利用してクローズ就労は可能です。ただ、障害者であることを開示して働くオープン就労に比べると、クローズ就労ではどうしても定着率が落ちてしまいます。そのため、メリット・デメリットの両方を理解してクローズ就労を選ばなければいけません。 それでは障害者がクローズ就労を行うとき、何を考えればいいのでしょうか。就労移行支援でのクローズ就労について解説していきます。 障害を開示せずに働くクローズ就労 障害者が一般企業で働くとき、最も難易度の高い方法にクロ…