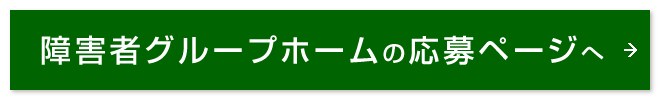就労継続支援A型の給料・年収・手取り:社会保険は加入できる?
障害の程度が軽度であるものの、一般就労が難しい場合、就労継続支援A型(就労A)を利用することで給料を得ることができます。就労Bの工賃とは異なり、最低賃金が守られて時給が計算されるため、それなりの賃金になります。
ただ短時間労働になるため、就労継続支援A型を利用するにしても一般就労に比べると給料・年収は少ないです。そうしたとき、平均月収はどれくらいになるのでしょうか。また実際の手取りや社会保険への加入はどのようになるのでしょうか。
就労Aを利用するとき、これらお金のことを事前に理解しなければいけません。そこで、就労継続支援A型での平均賃金や手取りについて解説していきます。
賃金はどこから?生産活動で得たお金が給料になる
まず、就労継続支援A型の賃金はどこから出ているのでしょうか。一般的には、生産活動で得たお金が給料になります。作業所によって仕事の内容は異なりますが、実際にビジネスをして商品・サービスを販売することで事業での売り上げを作るのです。

こうした生産活動によって売り上げを出した後、経費を引いたら利益が出ます。そうした利益の中から、給料・工賃が出されるのです。
・補助金から給料を払う事業所は多い
なお就労継続支援A型の場合、大半を国からの補助金頼みとなっています。これ自体は悪いことではなく、すべての障害福祉サービスは国からの補助金で運営が成り立っています。そのため場合によっては、生産活動は大きな赤字であるものの、国から得られる補助金を活用して利用者に賃金を出している事業所があります。
ただ障害者に支払う賃金については、国から得る補助金から出すのではなく、生産活動で得た収益を利用するように国から指示が出されています。そのため、収益性の低い就労Aは廃業に追い込まれやすいという実情があります。
・通常、体験利用で給料は発生しない
なお就労継続支援A型では雇用契約を結ぶものの、見学・体験利用のときは雇用契約なしで行うのが一般的です。このとき、体験利用で給料・工賃は発生しないのが一般的です。
平均賃金は月9万円ほど
それでは、就労Aで働くときの平均賃金(平均工賃)はいくらになるのでしょうか。年によって変動はありますが、厚生労働省の発表では以下のようになっています。
- 月9万円ほど
そのため、年収では以下のようになります。
- 月9万円 × 12カ月 = 年108万円
障害者向けの訓練施設であるため、就労継続支援A型で大きな収入を得ることはできません。就労Bよりは時給が大きいものの、就労Aだけで生活できるほどの給料を得るのは厳しいです。
最低賃金の時給は守られるが労働時間で給料が異なる
それでは、実際のところいくらの収入になるのでしょうか。就労継続支援A型では、雇用契約を結んで働くことになるため最低賃金が守られます。そのため就労継続支援B型よりも大きな給料・工賃を得られます。

ただアルバイトと同じように時給形式になるため、どれだけの労働時間や勤務日数なのかによって給料が大きく異なると考えましょう。例えば1日6時間について、週5日の通所であれば収入は以下になります(時給1200円と仮定)。
- 1日6時間 × 週5日 × 4週間 × 時給1200円 = 月14万4000円
一方、1日4時間にて週4日の勤務では以下のようになります。
- 1日4時間 × 週4日 × 4週間 × 時給1200円 = 月7万6800円
このように、月の給料は大きく違ってきます。A型作業所によって1日の労働時間は違いますし、何日の通所になるのかも障害者によって異なります。最低時給が存在するので賃金(時給)に大きな違いはありません。ただ、労働時間や勤務日数によって月給が大きく変わります。
障害者控除で非課税世帯となり、手取りは大きい
なお就労継続支援A型で働く場合、ほぼすべての人で非課税世帯になります。これは、障害者控除があるからです。障害者本人に対する控除は以下があります。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
| 障害者 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
※特別障害者は重度の障害者を指します
こうした控除があるため、1日6時間勤務を毎日したとしても、障害者控除によって住民税の非課税世帯に該当します。障害者というのは、一般企業にてフルタイム勤務をしない限り、ずっと非課税世帯のままと考えましょう。
所得税や住民税がないため課税がなく、手取りは大きくなります。また非課税世帯であるため、継続して障害者向けの特典を得つつ、就労Aを含めた障害福祉サービスの利用料は無料です。いずれにしても、就労Aで働いても障害者であれば税金(所得税・住民税)は発生しません。
健康保険はどうなる?雇用保険は対象
それでは、健康保険や雇用保険、労災保険などはどのようになるのでしょうか。障害者であっても、働いている人や無職の人を含めて、全員が国民健康保険に加入しています。そのため国民健康保険料を支払い、健康保険を活用しましょう。
健康保険料を支払うとその分だけ手取りは少なくなるものの、障害者では医療機関の受診が欠かせません。そのため、これについては仕方ないと考えなければいけません。
・働くことで雇用保険に加入する
なお一般的には、短時間労働であっても就労継続支援A型で働く人は雇用保険へ加入することになります。雇用保険に加入することで、就労Aをやめるときに失業保険の対象になるなどメリットが大きいです。以下のように、障害者は長い期間について失業手当を得られます。
| 雇用期間 | 1年未満 | 2~9年 | 10~19年 | 20年以上 |
| 一般受給者 | - | 90日 | 120日 | 150日 |
| 障害者:45歳未満 | 150日 | 300日 | ||
| 障害者:45~64歳 | 360日 | |||
就労継続支援A型では雇用契約を結ぶことになるため、労働基準法が適用され、最低賃金だけでなく雇用保険についても対象になります。
厚生年金加入(社会保険加入)は手取りが大幅減になる
なお前述の通り、就労継続支援A型で働く障害者は基本的に住民税の非課税世帯です。そのため所得税や住民税の支払いはありません。
ただ就労Aで働く障害者であっても、多くの人にとって影響をもつのが社会保険への加入です。低所得者にとって社会保険料の支払いは負担が大きく、手取りを大きく減らす要因になります。給料の約15%が社会保険料として取られるため、これによって大幅に手取りが少なくなるのです。
週20時間以上の労働をしている場合、社会保険(厚生年金)への加入対象になります。1日4時間、週5日の勤務で週20時間以上の労働に該当し、社会保険へ加入しなければいけません。住民税の非課税世帯であっても、社会保険料は対象になるのです。仮に1日4時間にて週5時間を働くと、以下の月給になります。
- 1日4時間 × 週5日 × 4週間 × 時給1200円 = 月9万6000円
ただ社会保険料によって約15%を引かれる場合、「9万6000円 × 15% = 1万4400円」が引かれ、手取りは月8万1600円となります。
基本的に税金を考える必要のない非課税世帯の障害者であるものの、唯一の例外が社会保険料です。就労継続支援A型で働く場合、要件を満たせば社会保険料の対象になることで、その分だけ手取りが大きく減ることを理解しましょう。
就労Aで得られる月収・年収を理解する
軽度の障害者であっても、最低賃金が守られる形で賃金を得られる就労継続支援A型は優れています。ただ時短勤務になるため、たとえ最低時給があるとはいっても、月の給料はどうしても少なくなりがちです。平均賃金(平均工賃)としては、月9万円ほどと考えましょう。
もちろん、労働時間と日数によって得られる収入は大きく変わります。また障害者控除によって、フルタイム勤務をしない限り、就労継続支援A型で働く人は住民税の非課税世帯に該当します。そのため、手取りは大きいです。
ただ非課税世帯の障害者であっても、週20時間以上の労働で社会保険の対象になります。雇用保険は多くの人で対象になりメリットは大きい一方、社会保険加入(厚生年金加入)では手取りがその分だけ減りデメリットが大きいことを理解しましょう。
就労継続支援A型を利用するとき、いくらの収入になるのか気になります。そこで「作業所で何時間働けるのか」「週に何日の通所をするのか」を確認しましょう。そうすれば、月に得られる給料を計算できるようになります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。
【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す
YouTubeでの障害者情報
Instagramでの障害者情報
TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。
【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集