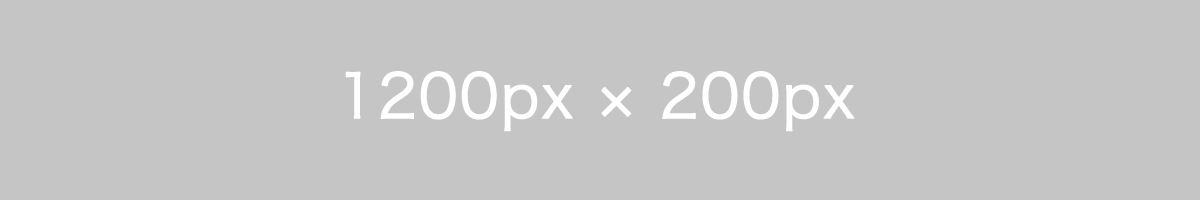共同生活援助で福祉専門職員配置等加算を得る資格の要件・基準
障害者グループホーム(共同生活援助)の運営を考えるとき、可能な限り加算を得ることで経営を安定させなければいけません。 そうしたとき、資格保有者が働くことによって得られる加算に福祉専門職員配置等加算があります。資格保有者の割合を満たすことにより、特に対策をしなくても、通常よりも多くの加算を算定できるようになるのです。 それでは障害者グループホームが福祉専門職員配置等加算を利用するとき、どのような要件になっているのでしょうか。福祉専門職員配置等加算の中身を解説していきます。 資格保有者がいると加算を得られる サービス管理責任者を除き、障害者グループホーム(共同生活援助)で働くときは資格が不要です。…

共同生活援助で業務継続計画(BCP)の作成とひな形の利用
障害者グループホーム(共同生活援助)の運営で重要になる書類作成に業務継続計画(BCP)があります。感染症や災害などが発生したとき、素早く業務を再開させるための指針になります。 実際に感染症や災害が発生したとき、事前に作成した業務継続計画(BCP)の通りに動けるとは限りません。ただ、業務継続計画(BCP)を作成しないと減算の対象になるため、研修を含めて共同生活援助は感染症や災害への対策を行う必要があります。 それでは、どのように業務継続計画(BCP)を活用すればいいのでしょうか。BCPのひな形・テンプレートの利用を含めて解説していきます。 障害者グループホームで必要なBCP 基本的には、症状の重…

同一敷地内で複数の共同生活援助や他の障害福祉サービスを運営するには?
障害者グループホーム(共同生活援助)の運営をするとき、同一敷地内や隣接地を活用して他の棟を運営することがあります。 このとき、同一敷地内・隣接地にて複数の障害者グループホームを活用し、運営するのは一般的です。ただ、この場合は減算に注意しなければいけません。また、共同生活援助に加えて他の障害福祉サービスの事業所を開設することもできます。 それでは、障害者グループホームが存在する敷地内について、他の事業所をオープンするにはどう考えればいいのでしょうか。同一敷地内・隣接地での障害福祉サービスについて解説していきます。 同一敷地内・隣接地で複数棟の開設は一般的 ある程度の面積がある場合、賃貸でも自前で…

共同生活援助の定員:障害者グループホームのユニットとは何か?
障害者グループホーム(共同生活援助)の経営では、定員やユニットについて理解しなければいけません。開業した後は関係ないですが、開業前や棟数拡大を考えるとき、定員やユニットを理解するのは重要です。 建物の構造によってユニットが異なります。またユニットが違えば、必要な人員配置や得られる報酬も違います。 それでは、障害者グループホームの定員やユニットはどのようになっているのでしょうか。共同生活援助での開業や増設で重要になる定員・ユニットについて解説していきます。 障害者グループホームのユニットとは まず、ユニットとは何でしょうか。ユニットとは、「利用者が生活するために必要な設備が整っている建物の単位」…

共同生活援助で住居追加・ユニット増・増設の流れ
障害者グループホーム(共同生活援助)の経営では、棟数を増やすことで、複数のグループホームを運営するのが基本です。入居者が少ないと利益を得ることができず、むしろ赤字経営になるリスクが高いです。 そこで、共同生活援助では積極的に住居追加・ユニット増をしなければいけません。そうしたとき、どのように増設をすればいいのか悩みます。 既に共同生活援助を運営している場合、サービス管理責任者やその他の職員を既に雇えているため、新規開業に比べると増設は容易です。ただ考えるべき点があり、どのように共同生活援助で住居追加すればいいのか解説していきます。 住居追加・ユニット増は一般的 一般的に障害者グループホームは利…

共同生活援助で夜勤職員加配加算を得る日中支援型の要件
障害者グループホーム(共同生活援助)の中でも、重度の人のみ受け入れる施設に日中支援型グループホームがあります。日中サービス支援型の場合は昼間や夜間を含めて、24時間スタッフが常駐することになります。 そうしたとき、夜間に追加でスタッフを配置することで得られる日中サービス支援型のための報酬に夜勤職員加配加算があります。 ただ、何も考えずに夜勤職員加配加算を算定すると微妙です。そこで、どのように考えて夜勤職員加配加算を活用すればいいのか解説していきます。 日中支援型グループホームで利用できる加算 すべての日中支援型グループホームについて、夜間支援従事者を配置しなければいけません。また、平日の昼間に…

共同生活援助で土日祝日・休日の人員配置はどうなる?
障害者グループホーム(共同生活援助)を運営するとき、多くのケースで土日祝日に利用者(障害者)は施設内で過ごすことになります。平日は日中活動をしているものの、土日は日中活動が休みになるからです。 そうしたとき、障害者が施設内で過ごしているのであれば、たとえ土日であっても利用者の支援を行いましょう。 それでは、どのように考えて障害者グループホームは土日の支援を行えばいいのでしょうか。共同生活援助での土日の支援について解説していきます。 土日でも人員配置が必要 多くの場合、障害者は平日の昼間に日中活動をします。就労や生活介護など、人によって日中活動の内容は異なります。また、必ずしも毎日の日中活動にな…

共同生活援助で帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算を請求する外泊内容
障害者グループホーム(共同生活援助)を運営すると、外泊として利用者が家族のもとに一時的に帰宅することがよくあります。 多くの場合、障害者は自ら適切に帰宅・外泊の準備をすることができません。ただ、共同生活援助の職員が帰宅の準備や家族との連絡・調整、交通手段の確保などを行うことにより、障害者は帰宅・外泊が可能になります。 こうしたとき、算定できるのが帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算です。そこで、どのように帰宅時の報酬を請求すればいいのか解説していきます。 家族との帰宅時・外泊時に請求 障害者グループホームが利用者を支援することにより、基本報酬を算定できます。ただ利用者が一時的に帰宅するとき、基本…

共同生活援助の入院時支援特別加算・長期入院時支援特別加算の内容
障害者グループホーム(共同生活援助)を運営するとき、利用者(障害者)が入院してしまうことがよくあります。入院によって障害者グループホームは報酬を算定できません。 ただ入院中の利用者に対して、適切な支援を行えば基本報酬とは異なる内容にて請求できます。そうした入院中に関する加算に入院時支援特別加算・長期入院時支援特別加算があります。 それでは、利用者が入院したときにどのように加算を活用すればいいのでしょうか。入院時支援特別加算・長期入院時支援特別加算について解説していきます。 利用者の入院で算定できる加算 利用者(障害者)が病院へ入院する場合、一般的には家族が支援します。健常者であっても、病院へ出…

共同生活援助で避難訓練は義務!正しい訓練の考え方や準備
障害者グループホーム(共同生活援助)を運営するとき、さまざまな制約があります。その中の一つが避難訓練です。 規模の大きい障害者グループホームでは、消防法で避難訓練が義務付けられています。ただ規模の小さい障害者グループホームであっても、消防法とは異なる指針によって避難訓練を実施しなければいけません。つまり、すべての共同生活援助で避難訓練が必須です。 それでは、どのように考えて障害者グループホームで避難訓練を実施すればいいのでしょうか。共同生活援助での避難訓練について確認していきます。 障害者グループホームで避難訓練は必須 消防法では、特定の施設について防火管理者の設置を義務付けています。障害者グ…