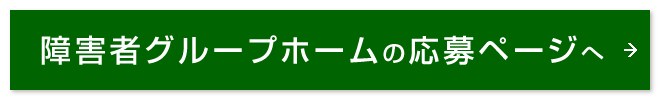心身障害者扶養共済制度の掛金や所得控除、メリット・デメリット
障害者をもつ親では、すべての人で親亡き後問題が存在します。こうした親亡き後問題を解決する一つの方法に心身障害者扶養共済制度があります。障害者をもつ家庭のみ利用できる公的な制度となっています。
月2万円(または月4万円)を障害者が死ぬまで受け取ることができたり、掛金について所得税・住民税を控除できたりと、メリットの大きい内容になっています。お金を受け取っても生活保護の収入認定とは関係ない点も優れています。
一方でデメリットもあります。途中解約する場合、支払ったお金はほとんど返ってきません。また、少なくとも20年以上は掛金を払い続ける必要があります。
メリットはあるものの、デメリットを含めて理解しなければいけません。そこで、心身障害者扶養共済制度の中身を解説していきます。
心身障害者扶養共済制度で毎月2万円の終身年金を作る
障害者をもつ子供がいる場合、親亡き後問題を心配するのは普通です。実際のところ、障害者が受け取る年金だけで安心した生活を送るのは不十分なケースが多いです。そこで、いまのうちに「親亡き後であっても障害をもつ子供がお金を受け取れる仕組み」を作っておくのです。
例えば障害者グループホームへ入居しておけば、65歳以上であっても障害者はずっと住み続けることができます。

ただこうした施設で格安にて住めるとはいっても、実費にて食費や水道光熱費がかかります。そうしたとき、年金に加えて月2万円などのお金を得る仕組みがあれば、障害をもつ子供は死ぬまで問題なく生活できるというわけです。
心身障害者扶養共済制度というのは、対象の障害者が死亡するまで月2万円(または月4万円)を受け取る仕組みを作るための制度です。障害者専用の終身年金が心身障害者扶養共済制度なのです。
税制優遇のある公的制度で所得税・住民税が減る:受け取りは非課税
重要なのは、心身障害者扶養共済制度は公的制度であることです。そのため優遇措置があり、障害者が死ぬまで受け取れる年金を作れるだけでなく、所得税・住民税を減らすことができます。
心身障害者扶養共済制度の加入者(保護者)が支払う掛金について、税制優遇を受けられます。そのため高額所得者であるほど、心身障害者扶養共済制度を利用する意義は大きいです。
生命保険を利用して所得控除は可能ですが、控除対象となる掛金の額は非常に低いです。それに対して心身障害者扶養共済制度であれば、掛金の全額が控除されます。例えば年20万円の掛金を支払っている場合、課税所得から20万円分が引かれるため、大幅に所得税と住民税が減ります。
一方、心身障害者扶養共済制度によって障害者がお金を受け取るとき、非課税となります。つまり、障害者は所得税や住民税を考慮する必要がありません。
親がお金を支払うときは税金が控除され、障害者がお金を受け取るときは非課税となるため、税金面では心身障害者扶養共済制度を利用するメリットは大きいです。
生活保護で収入認定されないメリット
また将来、生活保護となる場合であっても心身障害者扶養共済制度を利用するのはメリットが大きいです。
通常、生活保護費が支給される場合は収入から減額されます。例えば月13万円の生活保護費を受け取るとき、月8万円の収入(または年金)がある場合、支給される生活保護費は月5万円となります。
一方で心身障害者扶養共済制度については、生活保護費とは関係なくお金を受け取ることができます。そのため生活保護費が月13万円であり、心身障害者扶養共済制度で月2万円を受け取れる場合、月に利用できるお金は15万円になります。

労働収入だけでなく、年金であっても生活保護では支給額が考慮されます。一方、心身障害者扶養共済制度は生活保護で得られるお金とは無関係である点が優れています。
途中解約・弔慰金でほとんどお金が返ってこないデメリット
それでは、心身障害者扶養共済制度のデメリットとしては何があるのでしょうか。一番大きなデメリットとして、「途中解約によってほとんどお金が返ってこない」ことがあげられます。
・脱退一時金は非常に低い
途中解約によって返ってくるお金を脱退一時金といいます。掛金の支払い年数によって脱退一時金が異なりますが、以下のようになっています。
| 加入期間 | 脱退一時金 |
| 5年未満 | 0円 |
| 5年以上~10年未満 | 75,000円 |
| 10年以上~20年未満 | 125,000円 |
| 20年以上 | 250,000円 |
例えば掛金が月15,000円であり、10年加入すると支払総額は180万円です。
- 15,000円 × 12か月 × 10年 = 180万円
加入10年では125,000円が脱退一時金であるため、約93%のお金が没収されることになります。支払総額のうち、約7%のお金しか戻ってこないため、途中解約は絶対に避けなければいけないとわかります。
・弔慰金も非常に低い
また、親よりも先に「障害者をもつ子供が死亡するケース」もあります。確率は低いものの、こうした事態もあるのです。この場合、弔慰金としてお金が戻ってくるものの、弔慰金も非常に低い金額となっています。
以下は弔慰金の金額です。
| 加入期間 | 脱退一時金 |
| 1年未満 | 0円 |
| 1年以上~ 5年未満 | 50,000円 |
| 5年以上~20年未満 | 125,000円 |
| 20年以上 | 250,000円 |
このように、脱退一時金と同じくほとんどお金が戻ってこないとわかります。
障害者をもつ子供が親よりも長生きする必要があるため、致死性の高い難病をもつ子供については、心身障害者扶養共済制度を利用する意味はないです。一方で知的障害者や精神障害者、身体障害者などで致死的な疾患をもたない場合、心身障害者扶養共済制度を利用する価値は高いです。
20年以上は払い続ける必要がある:支払金額の中身
他には、支払期間が非常に長いことも心身障害者扶養共済制度のデメリットです。支払いが終わる(掛金の免除)になるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 加入後、20年以上が経過
- 65歳以上(実際には少し複雑ですが、ザックリ65歳以上と考えればいいです)
例えば30歳で加入する場合、35年が経過して65歳になることで掛金の支払いが終わります。一方で50歳で加入する場合、20年後の70歳で掛金の支払いが終わります。65歳以上になっても、20年が経過する70歳まで支払いが必要なのです。
脱退一時金は非常に低く、さらには長期間ずっとお金を払い続けなければいけないため、いずれにしても掛金の支払い停止が起こらないようにしましょう。
なお毎月の掛金額は親の加入年齢によって違っており、以下のようになっています。
| 加入者の年齢 | 掛金額 |
| 35歳未満 | 9,300円 |
| 35歳以上~40歳未満 | 11,400円 |
| 40歳以上~45歳未満 | 14,300円 |
| 45歳以上~50歳未満 | 17,300円 |
| 50歳以上~55歳未満 | 18,800円 |
| 55歳以上~60歳未満 | 20,700円 |
| 60歳以上~65歳未満 | 23,300円 |
心身障害者扶養共済制度を利用する場合、可能な限り45歳未満で加入しましょう。そうすれば、あなたが65歳になるとき、掛金の支払いはなくなります。
なお上記の表は一口にて加入するときの掛金です。一口の場合、月2万円の終身年金となります。心身障害者扶養共済制度は二口まで加入でき、この場合は月4万円の終身年金です。
・減額措置の内容
なお場合によっては、掛金の減額が認められます。例えば東京都心身障害者扶養共済制度の場合、加入者が以下のときに一口目の掛金が半額になります(二口目は減額とならない)。
- 生活保護または住民税の非課税世帯
- 自然災害など、知事が減額を必要と認める場合
場合によっては、こうした減額措置を利用することは可能です。
保護者の死亡または重度障害者になった月から支払われる
それでは、どのようなタイミングで障害をもつ子供に年金として月2万円(または月4万円)の終身年金が支払われるのでしょうか。あなた(親)が以下の状態になったとき、障害をもつ子供に年金が支払われるようになります。
- あなたが死亡した
- あなたが重度障害状態に陥った
なお、「親が重度障害に陥った状態」というのは、具体的には以下を指します。
- 両眼の視力を完全・永久に失った
- 言語機能を完全・永久に失った
- 両耳の聴力を完全・永久に失った
- そしゃくの機能を完全・永久に失った
- 両腕または両足を関節以上で失った
- 片腕を手関節以上で失い、かつ片足を足関節以上で失った
- 両腕または両足の機能が完全にない
- 10本の手指を失った、または完全に機能しない
この基準については、障害者手帳の基準とは異なります。いずれにしても、死亡または重度の障害を負った時点から障害をもつ子供に対して年金の支払いが始まります。
・支払額よりも受取額が低くなる可能性
こうした制度になっているため、あなた(親)が健康で長期間生きる場合、障害をもつ子供が受け取れる年金額は少なくなります。親が健康で生きていることは素晴らしいものの、お金の面だけで考えるとマイナスなのです。
またあなたが死亡した後、比較的早い段階で障害をもつ子供が死亡する場合、総支払額よりも年金受取額のほうが低くなります。
ただ、これについては大きなデメリットではありません。年金というのは、元々がそういう制度だからです。「たとえ生活保護を受けても、上乗せしてお金を受け取れる仕組みを親が生きているうちに作れる」ことに大きな意味があります。
・情報の共有は重要
それよりも重要なのは情報の共有です。親の死亡後に子供は年金を受け取れるようになるため、心身障害者扶養共済制度に加入していることを他の誰かに伝えておく必要があります。
子供の判断能力が問題ない場合、子供に伝えておけばいいです。一方で重度の知的障害者であれば、信頼できる第三者に伝えておくことで、親の死後に必ず心身障害者扶養共済制度を利用できるように準備しておかなければいけません。
保護者(親)の加入条件は何があるのか
それでは、実際に心身障害者扶養共済制度へ加入するときはどのような要件となっているのでしょうか。以下は加入者(親)の条件です。
- 障害者を扶養している親
- 加入者(親)の年齢が65歳未満
- 加入者(親)に特別な疾病や障害がない
要は、65歳未満で健康状態に問題がなく、障害をもつ子供がいる場合は心身障害者扶養共済制度への加入資格があります。
制度を利用して年金を受け取れる障害者の要件
また障害者についても加入条件があります。軽度の障害者で自立が可能な人は認められず、将来にわたって独立生活が困難な人が対象になります。例えば、障害者グループホームなどの施設でずっと生活するのが適切な人は加入できます。
障害者についての年齢制限はありません。ただ、独立した生活が困難な障害者である必要があります。このとき、以下の障害者が心身障害者扶養共済制度の対象となります。
- 知的障害者(療育手帳の保持)
- 身体障害者手帳で1~3級に該当する人
- 精神・身体に永続的な障害があり、障害の程度が上記1.または2.と同等(例:統合失調症、脳性まひ、自閉症など)
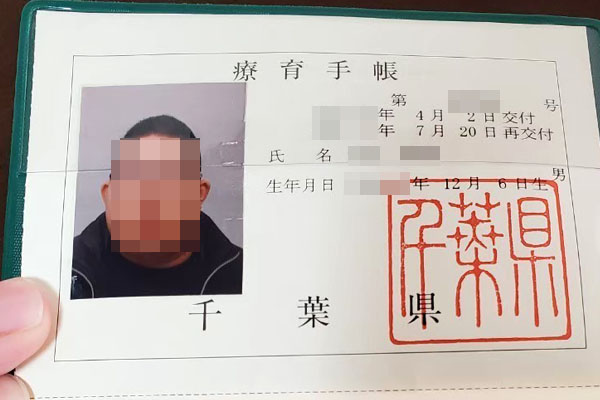
実際のところ、軽度の障害者であっても自立が困難な人は多いですし、年齢が高い障害者だと一人で生きていくのが難しいです。そのため実際には、多くの知的障害者や精神障害者、身体障害者で利用できる制度となっています。
一般企業への就職が難しかったり、障害者グループホームで過ごしていたりするなど、一人暮らしが厳しい障害者であれば、基本的には利用できると考えましょう。
心身障害者扶養共済制度で親亡き後問題に備える
障害者にとってお金の問題は重要です。障害者の多くは低収入であるため、何も対策をしないと生きていくことができません。そこで親亡き後問題を解決するため、心身障害者扶養共済制度を検討しましょう。
心身障害者扶養共済制度を利用すると掛金の分だけ課税所得が少なくなるため、所得税・住民税が低くなります。一方、障害をもつ子供がお金を受け取るときは非課税です。生活保護を受ける場合であっても、収入の対象外です。
こうしたメリットはあるものの、「途中解約や弔慰金で戻ってくるお金が非常に少ない」「少なくとも20年以上は支払いが必要」などのデメリットがあります。
これらのメリットとデメリットを考慮して、加入条件を満たしているのであれば心身障害者扶養共済制度を利用しても問題ありません。障害をもつ子供に終身年金を作りたい場合、公的制度である心身障害者扶養共済制度を有効活用しましょう。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。
【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す
YouTubeでの障害者情報
Instagramでの障害者情報
TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。
【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集