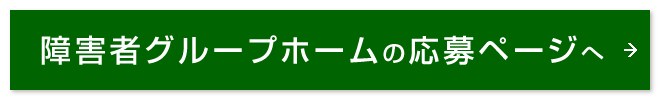共同生活援助で住居追加・ユニット増・増設の流れ
障害者グループホーム(共同生活援助)の経営では、棟数を増やすことで、複数のグループホームを運営するのが基本です。入居者が少ないと利益を得ることができず、むしろ赤字経営になるリスクが高いです。
そこで、共同生活援助では積極的に住居追加・ユニット増をしなければいけません。そうしたとき、どのように増設をすればいいのか悩みます。
既に共同生活援助を運営している場合、サービス管理責任者やその他の職員を既に雇えているため、新規開業に比べると増設は容易です。ただ考えるべき点があり、どのように共同生活援助で住居追加すればいいのか解説していきます。
住居追加・ユニット増は一般的
一般的に障害者グループホームは利益率が高くありません。また入居者数が少ないと人件費よりも支出が大きくなって赤字になりますし、一棟目では利益がほぼゼロのケースは多いです。

そのため、経営者は積極的に棟数拡大を考えなければいけません。
・サテライトを含め、開設したいグループホームを検討する
そこで、どのような形態にて増設するのか考えましょう。一般的には介護サービス包括型での一軒家ですが、ワンルームやサテライトを検討してもいいです。ワンルームは難易度が高いものの、軽度の障害者にとっては非常に人気です。
また日中支援型グループホームを検討してもいいです。人材確保や障害者への対応などの難易度は高いものの、介護サービス包括型に比べると日中支援型は利用者を非常に集めやすいです。いずれにしても、どのような形態にて増設するのか決める必要があります。
大まかな増設の流れ
それでは、実際に住居追加・ユニット増を行うときの流れはどのようになるのでしょうか。自治体によって内容は異なりますが、ザックリと以下のようになります。
- 自治体の保健福祉局や専門家(行政書士など)に確認
- 住居追加できる不動産を見つける
- 必要書類を集め、自治体で確認
- 申請受理で運営開始
補助金で成り立つビジネスであるため、非常に長いステップを踏む必要があります。そこで、増設の流れを確認しましょう。
自治体の保健福祉局や専門家(行政書士など)に確認
まず、都道府県の保健福祉局にて障害者グループホームの増設予定があることを相談し、今後の流れを確認しましょう。
ただ、このときは同時に市区町村や行政書士などの専門家などにも事前に確認しておくといいです。専門家については、その地域に根付いており、さらには障害福祉サービスに関する申請許可を何度も取り扱っている人がいいです。

同じ市区町村の都市で増設するなら何も問題ないですが、異なる都市での住居追加をする場合、必ず事前の確認が必須です。理由としては、「そもそも開業許可が下りない」という状況を避けるためです。
例えば横浜市や川崎市は非常に開業が難しく、ほとんど開業許可が下りません。こうした都市でなくても、「知的障害者向けなら開業許可が下りやすいものの、精神障害者向けでは許可がほぼ下りない」などの地域もあります。
地域による障害者グループホームに対する違いは大きく、障害福祉に手厚い地域があれば、承認がほぼ下りず障害福祉に厳しい地域もあります。そこで、「そもそも開業許可が下りるのか」を最初に確認しなければいけません。
住居追加できる不動産を見つける
実際にヒアリングしたあと、棟数拡大を行うために不動産を探しましょう。一般的には、一軒家でもワンルームでも賃貸にて不動産を探すことになります。
実際に不動産を探すとなると、利用者やスタッフからの利便性を考え、可能な限り良い立地である必要があります。例えば以下になります。
- コンビニやスーパーから近い
- 駅から近い
- 医療機関へ通いやすい
また、開設しているなら既に理解していると思いますが、以下の条件に合致する物件である必要があります。
- 延床面積が200m2以下
- 一部屋が7.43m2(約4.5畳)以上
- 市街化調整区域でない
ただ良さそうな物件があっても保証会社の許可がおりず、開設可能な物件になかなかたどり着けないケースは多いです。これがワンルームとなると、消防法との兼ね合いでさらに難易度が高くなります。いずれにしても、物件探しが非常に重要になります。
必要書類を集め、自治体で確認
そうして開設できる都市を把握し、物件を探したら、実際に書類を集めます。集めるべき書類は行政書士と確認しながら行うことになりますが、物件について建築図面、検査済証、建物の平面図などの書類を不動産会社から取得します。
その後、建物を管轄する市区町村の障害福祉課や消防署に相談し、開設予定の物件で共同生活援助を運営して問題ないかどうかを確認します。

開設では自治体・行政書士と密に連携しましょう。また自治体でヒアリングする場合、部署や担当者、連絡先を記録し、議事録に残しておくといいです。
申請受理で運営開始
なお、住居追加の届出は「変更日の前月15日まで」に受理してもらう必要があります。例えば9月1日にオープンしたい場合、8月15日までに届出が必要になります。
また、こうした届出を行う前に「内装工事(消防設備を含む)」「人員配置の確認」「家賃・食費・水道光熱費・日用品などの費用設定」などを行う必要があります。利用者から徴収する費用については、計算の根拠を提示できるようにしましょう。
そうして必要書類を提出し、受理されたら障害者グループホームの指定を受け、共同生活援助の運用開始になります。
障害者グループホームの開設では、増設であっても非常に多くの書類提出が必要になります。そこで大まかな流れを把握し、行政書士の力を借りながら進める必要があります。
障害者グループホームで住居追加を行う
住居追加・ユニット増により、入居できる部屋を増やすのは重要です。棟数拡大を行わないと障害者グループホームの経営につまづきやすいからです。
そこで増設をするとき、まずは自治体にて確認しましょう。また、地域性を理解するのも重要です。都市によっては障害福祉サービスに後ろ向きであり、共同生活援助の許可がほぼ下りないケースがあるからです。
開設に必要な内容を確認した後、実際に物件を探します。また物件を見つけたら、その物件での開設が問題ないかどうか市区町村の役所や消防署と相談しなければいけません。
そうして事前に準備を行い、届出が受理されたらオープンとなります。行うことは非常に多いですが、開設時と同様に適切なステップを踏むことで共同生活援助の増設が可能になります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。
【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す
YouTubeでの障害者情報
Instagramでの障害者情報
TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。
【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集