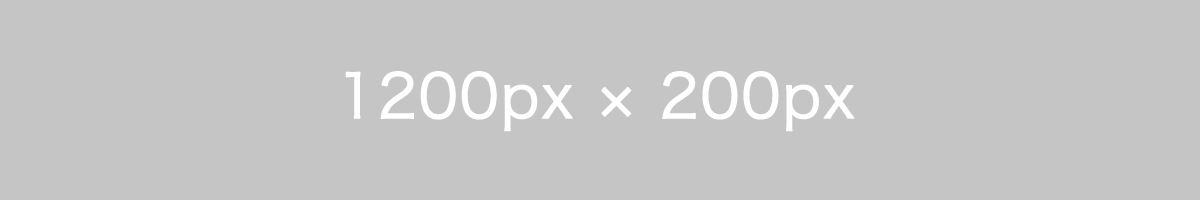生活介護の活動内容:一日の流れや過ごし方、スケジュール
重度の障害者が生活介護(デイサービス)を利用するとき、「施設内で何をするのか?」と気になる人は多いです。生活介護での活動内容を理解しないと、どのようなメリットがあるのかわかりません。 実際のところ、事業所によって活動内容は異なります。ただザックリとした内容はどこも共通しています。そこで一日の流れ・スケジュールをある程度まで知っておけば、どのようにデイサービスを活用すればいいのかわかります。 それでは、生活介護での過ごし方はどのようになるのでしょうか。障害者で利用されるデイサービスの活動内容について解説していきます。 デイサービスで障害者の機能向上を目指す 主に重度障害者が生活介護(デイサービス…

生活介護で行われるゲーム・レクリエーションの種類やイベントの中身
症状の重い障害者が主に利用する障害福祉サービスが生活介護(デイサービス)です。生活介護では障害者に対してレクリエーションがひんぱんに実施されます。 創作活動やゲームを通して、デイサービスでは障害者の生活機能や運動機能の改善が行われます。このとき、さまざまなレクリエーションが実施されます。 それでは生活介護で行われるレクリエーションとしては何があるのでしょうか。デイサービスで行われるレクリエーションやイベントについて解説していきます。 デイサービスで行われるレクリエーション 生活介護では、利用者(障害者)に対してさまざまなレクリエーションが行われます。重度障害者が生活介護を利用するため、健常者が…

生活介護(デイサービス)の送迎サービス:自宅以外や自己負担は?
生活介護(デイサービス)を利用する人は重度障害者が多いです。ただ生活介護は通所施設であり、重度障害者が自らの力で生活介護施設へ出向くのは現実的ではありません。 そうしたとき、ほとんどの生活介護施設で送迎サービスを実施しています。そのため障害者が生活介護へ自ら行く必要はないですし、家族が送り迎えをする必要もありません。なお中には送迎対応していない施設もあり、この場合は外出支援サービスを活用しましょう。 それでは生活介護での送迎サービスについて、どのように活用すればいいのでしょうか。デイサービスで行われる送迎について解説していきます。 ほとんどの生活介護施設で送迎がある 重度障害者が利用する生活介…

生活介護で病院への通院同行・通院介助は可能?
重度障害者では、生活介護(デイサービス)を利用している人がたくさんいます。また、こうした重度障害者の場合、定期的な通院が必要になる人が多いです。 このとき、「生活介護の利用中に医療機関への通院同行・通院介助は可能なのか?」と考える人がいます。これについて、その他の障害福祉サービスを利用すれば通院同行・通院介助は可能です。 それでは生活介護を利用している障害者が病院・クリニックへの通院同行を利用するにはどうすればいいのでしょうか。障害者について、医療機関への通院同行・通院介助の方法を解説していきます。 デイサービスで病院同行はサービスに含まれない 生活介護(デイサービス)を利用する人は主に重度障…

生活介護を受けるには?サービス利用の開始手続き
障害福祉サービスとして生活介護(デイサービス)を利用する人は多いです。生活介護は公的サービスであるため、事前にサービス利用を開始するための申請手続きをしなければいけません。 既に障害福祉サービスを利用している人の場合、簡単に生活介護を開始できます。ただ初めて障害福祉サービスを利用する場合、手続きには時間が必要ですし、どのように生活介護をスタートさせればいいのかわかりません。 それでは、生活介護を受けるにはどうすればいいのでしょうか。生活介護のサービス利用の開始手続きについて解説していきます。 重度の障害者で生活介護を利用できる 生活介護を利用するためには、ある程度まで重度の障害を有する必要があ…

知的障害者で生活介護へ通う活動内容や利用法
症状の重い障害者で利用される障害福祉サービスに生活介護(デイサービス)があります。そして、このような生活介護を利用する障害者の一つに知的障害者がいます。 症状の重い知的障害者がデイサービスを利用することにより、生活能力の向上を目指します。可能な限り自ら日常生活動作を行えるようにすることで、人間らしい生活を送れるようにするのです。 それでは知的障害者が生活介護を利用するに当たり、どのような活動内容になり、何を考えればいいのでしょうか。知的障害者がデイサービスを利用するときの活用法を解説していきます。 中等度・重度の知的障害者でデイサービスを利用する 一般的には、重度の障害者で生活介護(デイサービ…

精神障害・発達障害で生活介護(デイサービス)を利用する考え方
精神疾患を抱えている場合、精神障害者になります。うつ病・双極性障害や統合失調症、パニック障害、発達障害(ADHD、アスペルガー症候群、自閉症)など、人によって症状は異なりますが、こうした精神障害者はたくさんいます。 これら精神疾患を抱えており、さらには症状が重い場合、生活介護(デイサービス)の利用を考えます。日中活動の中でも、重度障害者向けの公的サービスが生活介護です。 それでは重度の精神障害者について、どのように考えて生活介護を活用すればいいのでしょうか。精神疾患を有する人について、デイサービスの利用法を解説していきます。 重度の精神障害者でデイサービスを利用する 通常、精神疾患は症状の度合…

生活介護での医療的ケア・健康診断:重症心身障害者は対応可能?
障害者が生活介護(デイサービス)を利用するとき、看護師が常駐していますし、場合によっては医師の配置もあります。これは、重度障害者が主に生活介護を利用するからです。 そのため施設によっては医療的ケアが可能です。すべての生活介護の事業所ではないものの、重症心身障害者を含めて受け入れ可能です。また医療従事者が働いているため、生活介護にて健康診断が実施されることもあります。 それでは生活介護での医療的ケアはどのようになっているのでしょうか。医療が必要な障害者について、どのように生活介護を利用すればいいのか解説していきます。 生活介護では看護師や医師(嘱託医)がいる 基本的には、生活介護では看護師がいま…

生活介護の日中活動で複数事務所・2か所利用にて併用可能?
重度障害者であれば、多くの人が生活介護を利用します。このとき、一つの生活介護施設に加えて他の障害福祉サービスを複数の施設で利用できないかと考えるのは普通です。 生活介護に加えて複数事業所を利用するとき、特定の障害福祉サービスであれば2か所利用が可能です。ただ日中活動系の障害福祉サービスについては、多くで生活介護と併用できません。 それでは、生活介護の利用者が他の障害福祉サービスを含めて2か所利用するにはどうすればいいのでしょうか。生活介護で複数事務所を利用するときの考え方を解説していきます。 生活介護の複数利用は可能 障害福祉サービスの複数利用について、まずは「2か所の生活介護事業所を利用する…

生活介護での入浴介助:利用頻度や入浴料はどうなる?
重度障害者であっても、日々の入浴は重要です。体を清潔に保つことで、衛生環境を整えることができるからです。 こうした重度障害者で日中に生活介護(デイサービス)を利用している人はたくさんいます。このとき、生活介護の事業所によっては入浴サービスを提供していることがあります。このとき入浴料が無料になることがあれば、入浴代の支払いが必要なケースもあります。 それでは生活介護での入浴介助について、障害者はどのように利用すればいいのでしょうか。生活介護で行われる入浴サービスの考え方について解説していきます。 重度障害者は入浴費用が無料 生活介護の施設によっては、入浴サービスを提供していることがあります。この…