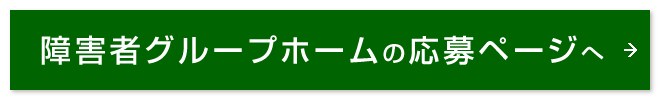身体障害者・精神障害者の生活保護で自動車を保有するには
身体障害者や精神障害者について、生活保護であっても車を保有したいと考える人がいます。自動車を運転することにより、さまざまな場所へ出向くことができます。
このとき、生活保護受給者は原則として自動車の保有が認められていません。ただ特定の条件を満たす生活保護受給者の場合、例外的に車の所有が認められるケースがあります。
それでは生活保護の身体障害者や精神障害者について、どのように自動車を利用すればいいのでしょうか。生活保護を受けている障害者の自動車保有について解説していきます。
原則、生活保護で車の保有は認められない
生活保護を受けている人について、資産をもつことが認められていません。そのため高額な預貯金や不動産、自動車の保有は禁止されています。
車を保有して運転している状態では、「自らの力で最低限の生活が可能」と判断されます。また中古であっても車には資産価値があり、売却することでお金になります。そのため、生活保護を受けるためには保有している車を売らなければいけません。
なお自動車を保有すると、車検やメンテナンス費用、ガソリン代、駐車場代、税金など、さまざまな費用を支払わなければいけません。そのため生活保護受給者が車を所有すると、生活費を支払えなくなる可能性があります。

また生活保護受給者が自動車保険に加入するとなると、金額が高すぎて支払えない人が多いです。そうなると、事故を起こしても自らの力で賠償できません。そのため障害者であっても、基本的に生活保護では車を保有してはいけないのです。
無断で所有すると生活保護停止のリスク
そのため「車がなければ生活できない障害者」を除いて、生活保護で車の保有を考えるのはやめなければいけません。
なお中には、「内緒で車を保有できないか?」と考える人もいます。ただ、これは不正行為になるのでリスクが高く、やめたほうがいいです。
もし福祉事務所の許可なしに車を保有していたことがバレると、生活保護が停止になるリスクがあります。それだけでなく、不正受給とみなされて、これまで支払われた生活保護費の返還を求められる可能性もあります。
不正行為は非常にリスクが高いです。そのため、生活保護受給者は許可なしに車を保有しないようにしましょう。
他人名義の車の運転も認められない
なお生活保護を受けている人について、「自分で車を保有できないのであれば、家族など他の人が保有する車を運転すればいいのでは?」と考える人がいます。
ただ生活保護受給者の場合、他人名義の車の運転も禁止されています。これは、レンタカーであっても同様です。
生活保護受給者が事故を起こすと、前述の通り適切な賠償を行うことができません。そのため、賠償責任の観点から他人名義の車であっても運転が認められていないのです。
生活保護の障害者で車所有が認められるケース
ただ身体障害者や精神障害者の中には、自動車を利用しないと生活が成り立たないケースがあります。この場合、認められれば例外的に車所有が可能になります。
障害者の場合、以下のケースであれば車を保有できます。
- 通勤・通院で公共交通機関を使えない
- パニック障害などで電車やバスに乗れない
- 6か月以内に生活保護からの脱却が見込まれる
このように、どうしようもない理由があったり、生活保護からの脱却が可能であったりする場合のみ車の所有が可能になります。
通勤・通院で公共交通機関を使えない
都市部に住んでいる場合、電車やバスを利用することによって移動できます。たとえ地方であっても、多くの都市でバスを利用できます。
ただ中には、非常に田舎の地域に住んでいる人がいます。こうした地方では、車がなければ通勤や通院をすることができません。

この場合、例外的に車の保有を認められるケースがあります。車がなければ移動できず、通勤や通院はできません。
生活保護では車の保有が原則禁止であるものの、障害者が生活保護から抜け出すための妨げになってはいけません。そのため公共交通機関を利用できないほどの田舎に住んでいる場合、福祉事務所へ相談しましょう。
パニック障害などで電車やバスに乗れない
また精神障害者によっては、車移動でなければ無理なケースがあります。うつ病や統合失調症など、精神疾患には種類があり、その中でもパニック障害の場合は公共交通機関の利用が難しくなります。
パニック障害の症状が重い場合、電車やバスなど人が多い場所へ行くことができません。発作が起こることで、移動どころではないからです。

この場合、「パニック障害によって電車やバスなどの公共交通機関を利用できない」という医師の証明があれば、福祉事務所と相談することで、車の保有を認められるケースがあります。
車所有が可能かどうかは福祉事務所の判断です。ただパニック障害で公共交通機関を利用できず、頼れる親族もいない場合、車を保有できる可能性が高くなります。
6か月以内に生活保護からの脱却が見込まれる
また軽度の精神障害者であったり、問題なく働ける身体障害者だったりする人に限定されますが、6か月以内に生活保護からの脱却が見込まれる場合、例外的に車の保有が認められるケースがあります。
都市部に住んでいる人を除いて、車通勤の人は多いです。この場合、車を保有しないことで就職が難しくなってはいけません。
そのため求職活動をしており、障害者雇用を含めて企業就職に向けた活動をしているのであれば、車の保有が認められるというわけです。
なお、求職活動以外を理由として車を保有する場合は認められません。あくまでも企業就職に向けて積極的に活動しており、半年以内に生活保護を抜け出せる人が車保有の許可が出る対象者になります。
生活保護の障害者で車を保有する
身体障害者や精神障害者が車を運転するのは普通です。ただ生活保護受給者の場合、原則として車の所有は認められていません。そのため、特定の条件を満たしている障害者のみ車を保有できるようになっています。
地方に住んでおり、電車やバスを利用できず、車がないと通勤や通院ができない場合は例外的に車を保有できます。またパニック障害で公共交通機関を利用できない場合であっても認められるケースがあります。この場合、家族の協力を得られないことが条件です。
また障害者雇用を含めて、求職活動によって社会復帰を目指しており、6か月以内に生活保護から抜け出せる見込みがある場合も車の所有が認められます。
生活保護で車の保有が認められるケースは限られます。そこで身体障害者や精神障害者について、認められるケースに当てはまっている場合のみ自動車の運転を考えましょう。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。
【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す
YouTubeでの障害者情報
Instagramでの障害者情報
TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。
【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集